徳島県南部、牟岐町に出羽島という周囲4km程度の小さな島があります。約4kmほど沖合にある島で江戸時代後期から人々の移住が進められ明治から昭和にかけてはカツオ、マグロ漁を中心とした漁業の島として活況を呈していました。近年は過疎化高齢化が進んでいますが漁村集落の古い町並みが残ります。そんな出羽島を訪ねました。
アクセスは牟岐港から連絡船で15分程度、船は1日6便あります。牟岐港まではJR牟岐駅から徒歩10分程度で着きます。車利用の場合連絡船乗り場の前と少し離れたところに駐車場(無料)があります。




料金は船内で精算するシステム、乗っていると船員さんが回ってきます。15分程度で到着です。
船を降りると木々が生い茂り少し見にくいですが「ようこそ出羽島へ」の案内板が迎えてくれます。目の前に漁村センター、隣に蛭子神社、向かい側に郵便局があります。




なかなか風情のある郵便局です。このあたりがメインストリートといったところでしょうか診療所もあります。診療所の隣に大正時代、島の青年会が中心となって創建された出羽神社があります。


出羽神社から少し歩くと津波避難用の「タスカルタワー」があります。徳島県南部、南海トラフ巨大地震への備えといったところでしょうか。周囲は趣のある集落になっています。


残念ながら空き家が多いようですがまさにタイムスリップしたような感覚になりゆったりとした時間が流れています。
集落の奥に勧栄寺というお寺があります。このお寺には嘉永7年(1854年)の大地震(一般的には安政南海地震と呼ばれている大地震)で津波が押し寄せた際、住民が山上に避難し難を逃れたことを神仏に感謝する内容が記された石碑があります。


安政南海地震に関しては海を隔てた和歌山県広川町で稲むらに火を放ち住民を高台に誘導した「稲むらの火」の物語をご存じの方も多いかと。
勧栄寺から「観光遊歩道の中央コース」を目指します。途中セルフサービスの休憩所がありもう少し歩くと共同井戸があります。井戸の近くではかつて「カニクイ(オオウナギ)」の生息が確認されたようです。

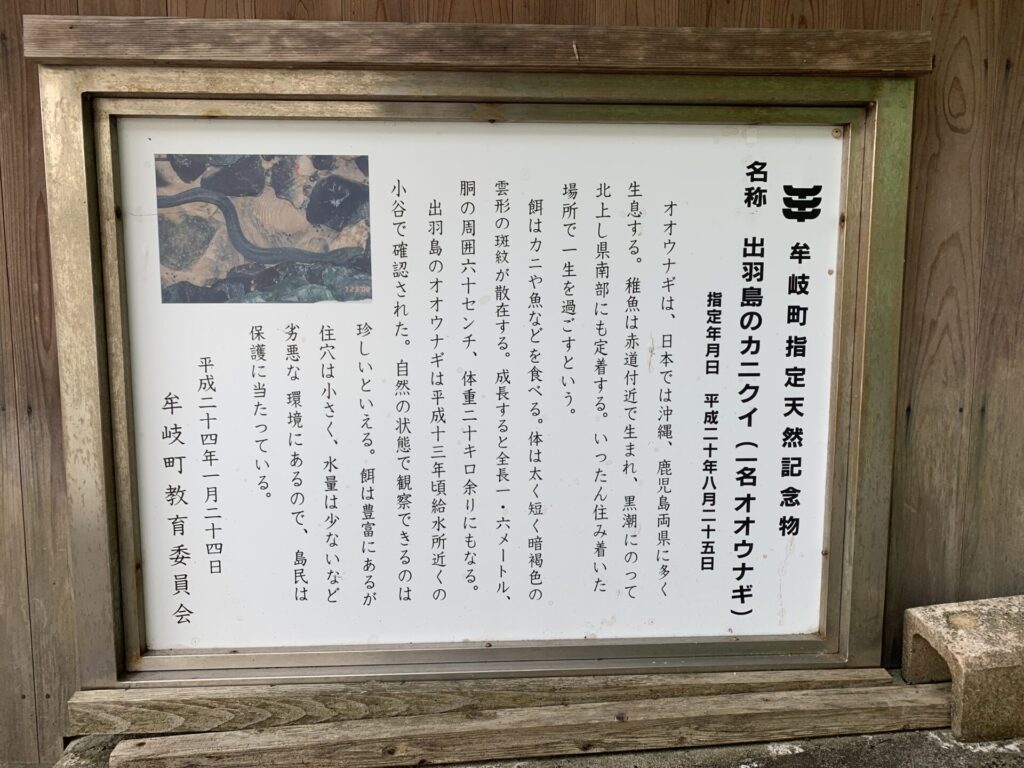
共同井戸のところが遊歩道と展望台の入り口になっています。まずは展望台に上ります。数えませんでしたがけっこう長い階段を上ります。


暑いなかきつかったですが港と対岸の風景が一望できます。遊歩道に戻りしばらく歩くと小学校跡への分かれ道があります。


小学校は平成5年から休校、同21年には閉校になったようです。現在は避難場所やヘリポートとして活用されているようです。
遊歩道に戻り出羽島灯台を目指します。遊歩道はところどころ雑草が茂っていますが比較的歩きやすいです。


出羽島灯台からは「観光遊歩道西回りコース」で戻ります。途中国指定天然記念物「シラタマモ」が国内で唯一自生している「大池」があります。


遊歩道にもどり船着き場を目指します。港の入り口を通りますが「石積みの大波止(堤防)」があります。
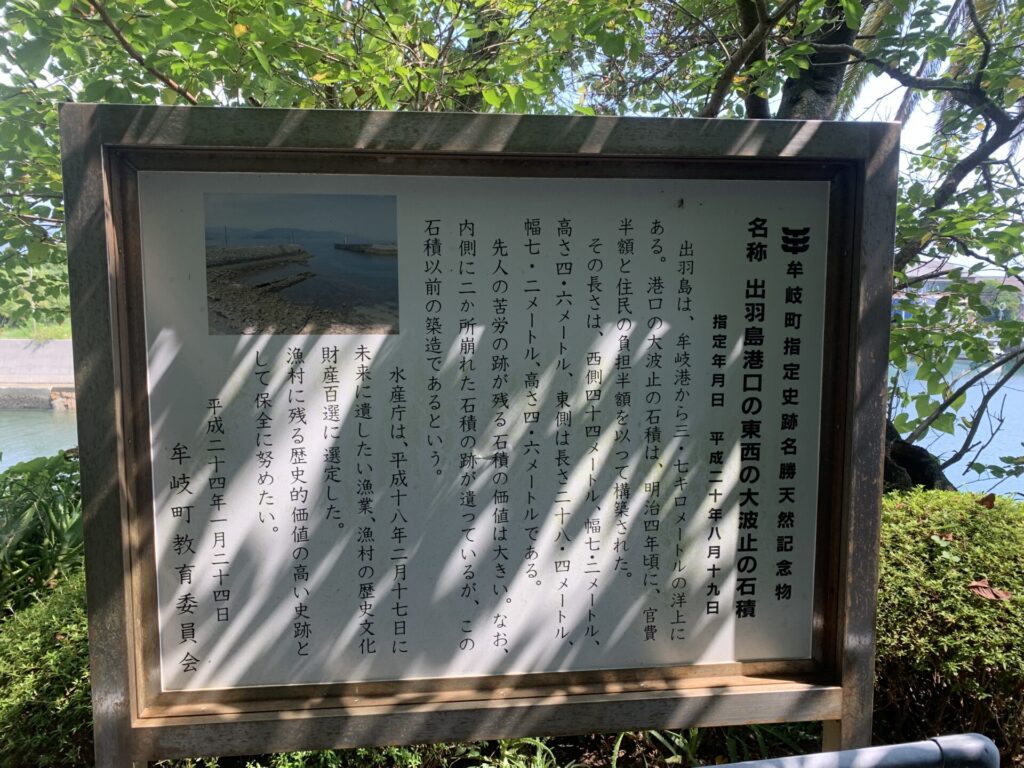

説明書きによれば明治4年頃に構築され「未来に遺したい漁業漁村の歴史文化財産百選」に選ばれているようです。
大波止からすぐのところに「大正沚発見の碑」があります。
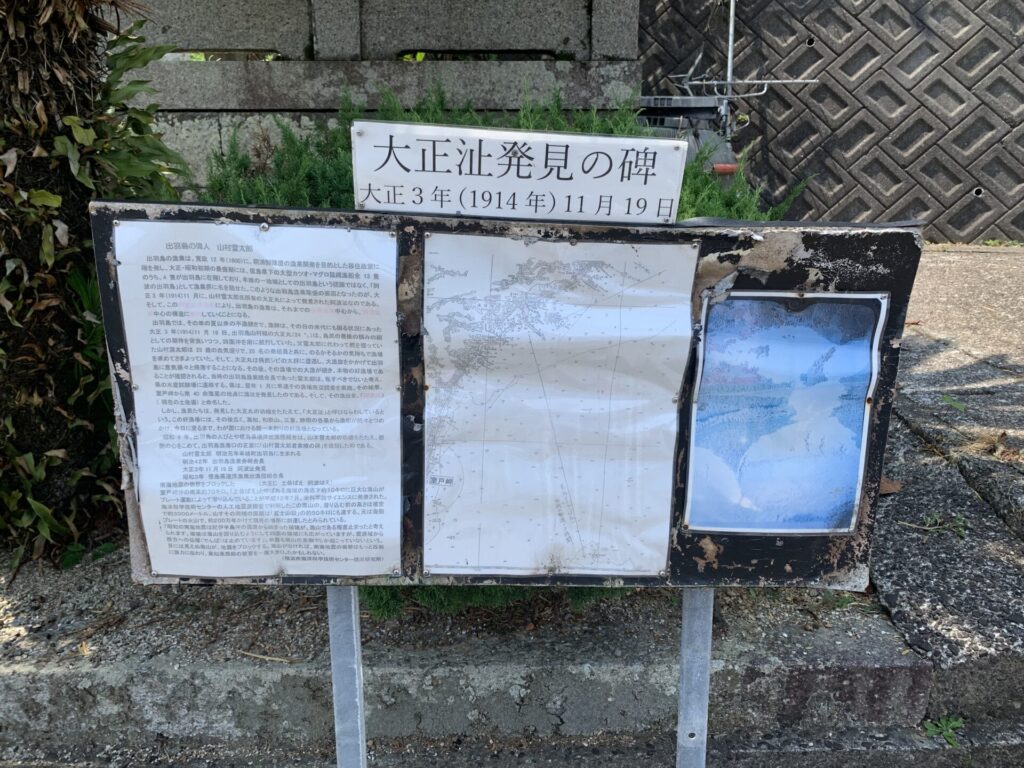

大正沚とも阿波沚ともいうようです。「沚」にはいろんな意味があるようですが浅い海底部ということのようです。説明書きの文脈から想像すると好漁場の浅い海底部を発見したということだと思います。この大正沚の発見(大正3年)により大正から昭和の初期にかけ出羽島の漁業は大いに栄えたようです。
概ね一回りといったところですが島のあちこちで見かけたものに「ネコ車(手押し車)」と民家の「ミセ造り(蔀帳)」があります。


車のない島、物資の運搬に欠かせないのがこのネコ車、2輪のものや4輪のものなど色んな形があり面白いです。ミセ造りとは上下に分かれた折りたたみ式の雨戸を用いた技法で上下に開いて使用、下の戸は下げると縁側になり、上の戸は蔀戸(庇)になります。ネコ車やミセ造りを見れただけでも来た価値はあったと思います。
徳島の離島、出羽島を訪ねました。明治期から昭和初期の建物も残る漁村集落は趣があります。人口は減少し島の方によると現在住んでいる人は40人に満たないそうですが、是非とも残していってもらいたいものです。遊歩道が整備されていて2時間程度で一回りできますがもう少し時間をとってゆっくり過ごすことをお勧めします。ただ食事ができるところが限られるので事前に確認するか準備するかが必要になると思います。懐かしい漁村風景が残る出羽島、是非訪ねてみてください。(各種交通機関、各施設等の情報は公式HP等で最新のものをご確認ください)


